こんにちは。人生100年時代”わくわく”ライフプランニングコーチのafroriansymです。
最近はいろいろなメディアが増えましたね。映像系の領域ではYoutubeやニコニコ動画だけでなく、AbemaTVやNetflix、AmazonTVなど。音声プラットフォームとしては、ネットラジオ系のサービスやHimalaya FM など。
私は夜中までAmazonTVを見過ぎて寝不足がちです。まだまだ、中学生時代に、夜中にラジオで”オールナイトニッポン”を聞いていたころ、高校生や大学生の時にケーブルテレビ(スペースシャワーTVなど)で音楽番組やWWE(プロレス)を見ていたころと変わっていないかもしれません。
メディアを通してみているもの(番組など)は違うと思いますが、どの年代も、夜中まで楽しむことができるもの。それは過去の偉人たちの発明のおかげです。そしてその発明の元となった学問(数学、物理学、化学、統計学、生物学、哲学、うんぬん)のおかげです。
単純にメディアなどを含めて現在はテクノロジーの恩恵を受けていますが、さらに発達した世の中になっていく時に、自分はどうすれば自分自身に価値を見出せるのか。非常に不安でもあります。
そんなところから手に取った本のお話し。
対象は中学生~の若者からベテランビジネスパーソンまで通じる内容です。
書籍: ミライの授業 (瀧本哲史 著)
おおっと、実は2016年発売の書籍なんですね。書店での置き方からして、新しいのかと思いこんでました。
本書を手に取った理由

きっかけ
お休みを頂いて朝から歯医者に行ったあと、書店をふらふらしていて見つけました。
エスカレーター降りて真っすぐ進むと、ビジネス書エリアの一番角の方に置いてあって、不思議と吸い込まれるように目にとまりました。
ボリューム的にも文字の大きさ的にも、すぐ読み込めそうだったので迷わず購入しました。(よし、すぐ読んで書評記事を書こう。的なやつです。)
なにより、自分の子どもたちが少し大きくなってきたときに、一緒にどのように考えてこれからの時代を生きていくと良いのかのヒントにしたいと感じさせる印象を受けました。
本書の帯に記載のあるキャッチコピーを引用しますとこんな感じです。
これは14歳に向けた「冒険の書」であり、
大人たちが知るべき「教養の書」である。
これはそそられる。14歳だけでなく、大人も読みたくなるじゃないですか。きっちり広い層に向けたアピール、素晴らしいです。
私の息子たちはまだ幼稚園ですが、これから冒険をどんどんしていきます。あっという間に14歳になるでしょう。
親としては、正しく冒険の書を記録するためのサポートと、冒険を始めるための地図を与えておかねばならぬ。そんな思いにさせられて購入しました。
完全に、ドラゴンクエストやらをイメージさせられてまんまと乗せられましたね。
(SUCCESSs(過去記事参考)でいうと何がポイントでしょうかね。)
読む前に得たいと考えたこと
ところで、もし、あなたが子ども達に「学ぶ理由」を聞かれた場合は何と答えるでしょうか。
個人的には、今のテクノロジー化した便利な社会に住むことができるのは、過去の人間たちが学んできた内容のお陰であることを知るためだよ、というお話をしようと考えていました。
まあ実際に、長男にはもっと簡単に、軽く話したことはあります。しかし反応はイマイチだったかな。私の伝え方がイマイチだったのと、話すタイミングがよろしくなかったのだと思います。
なので、今の生活は過去の人間の発見の積み重ねで成り立っているのだ!と伝えるだけでは、学ぶモチベーションを高めることは難しいのではと考えていました。なんか結局、義務感しか生まない答えになっているのではと感じていたわけです。
(そういえば、私の伝え方には子どもでもわかる”SUCCESs”が無かった。。。)
本書によって、子どもたちとワクワクしながら学ぶ理由を見つけて、腹に落としたいと思い購入しました。
本書の概要

ポイントは”なぜ学ぶのか”
思い込みを抜け出して「あたらしい世界」をつくるために学ぶ。ということが、”なぜ学ぶのか”に対する答えだと思います。
いきなりそんな一言で答えを書いても何のことやらでしょう。
本書の冒頭で、こんな問いかけがあります。皆さんはどんな言葉が”?”の中に入ると思いますか?
法則1 世界を変える旅は「?」からはじまる
法則2 冒険には「?」が必要だ
法則3 一行の「?」が世界を変える
法則4 すべての冒険には「?」がいる
法則5 ミライは「?」の向こうにある
ちなみに上記の5つの法則は、「未来をつくる5つの法則」と題して、筆者が14歳の様々な中学生に向けて語りかけたものだそうです。中身は、普段筆者が講義をしている、京都大学の学生たちへ向けたものと変わらないということ。
答えは後のほうで。”なぜ学ぶのか”というポイントに戻ります。
筆者は、現代のテクノロジーが非常に発達した便利な社会を、「魔法の世界」と表現しています。
スマホ1台で、音楽を聞いたり、ノートをとったり、本も読むことができるしゲームなどの娯楽も楽しめます。昔は机にばらばらと置いてあった音楽機器やゲーム機械、それに本やノートが必要ありません。
そんな、「魔法」が現実のものになっているのは、「魔法の基礎」を学んできたからこそなのです。その”「魔法の基礎」が、学校で学ぶこと”。というわけです。
基礎を学ばないことには、新しい世界を作り上げていくには時間がかかります。
例えば、数学の2次方程式の解の公式。あの公式を知らない場合に、自分で公式を発見することもできなくはないかもしれません。ただそれはさすがに時間がもったいないでしょう。(自力で公式を発見する力があるのであれば、もっと先端の知識を学び、新しい発見を切り開く力があるのではないでしょうか、という意味です。自力で発見できる人のすごさは当然あると思います。)
基礎を学ぶ中で、「これってそもそもなんで?」とか、疑問がわいてくることもあるかと思います。基礎自体が誤っている可能性もゼロではありません。
同じように、世の中のサービスに対してなど、なぜこれがないんだろう。もっと便利になるんではなかろうか。など考えるきっかけ、基礎を知ってこそ気づく部分が出てくるからではないでしょうか。電話、蓄音機、自動車や飛行機などから、いまでは携帯電話、スマートフォンなどができた背景もそのようなきっかけがあるのではないでしょうか。
既存の価値観や常識に対して、真っすぐに疑問を持って考えることができる人。それこそが新しい世界をつくっていくことができる人だと感じます。
新しい世界をつくる、未来を創る、というと大層ですね。でも言い換えれば、未来を楽しく生きる、ということなのかなと感じています。大人も子どももみな一緒に。
そのための考え方をインストールすることができる良書です。
関連書籍として思い浮かんだもの
今回ご紹介している、「ミライの授業」を読み進めている時に強く感じた点があります。
ストーリー性が強いです。歴史上の人物の物語を多く引き合いに出しています。身近に感じることができるように配慮したのか、中学生でも知っている人物の例が多めです。
文章の表現もわかりやすく、14歳にすんなり入る表現となってます。まさにこれは、最近読んだ書籍の内容と重なるなと感じました。
さらに、数学的帰納法の父、フランシス・ベーコンがちらっと出てきました。これからの時代は、「統計学」を、帰納法とあわせて子ども達に学んでおいて欲しいなと感じました。事実を積み重ねた結果を分析する。それで誰かを説得することもあれば、新たな発見の手がかりとすることも多いでしょう。
というわけで関連書籍です。
「アイデアのちから」、と、「完全独習 統計学入門」 です。

- 作者: チップ・ハース,ダン・ハース,飯岡美紀
- 出版社/メーカー: 日経BP社
- 発売日: 2008/11/13
- メディア: 単行本
- 購入: 27人 クリック: 274回
- この商品を含むブログ (74件) を見る

- 作者: 小島寛之
- 出版社/メーカー: ダイヤモンド社
- 発売日: 2006/09/28
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- 購入: 215人 クリック: 3,105回
- この商品を含むブログ (115件) を見る
いずれの書籍に関しても、過去記事を書いてます。
是非ご覧頂けますと幸いです。
www.afroriansym100life-shift.net
www.afroriansym100life-shift.net
さあまだまだいきましょー。
実践すること

歴史上の人物から学ぶことを実践します。
具体的には、偉人の伝記を読んで、本書の概要に書いたポイントにあてはまるかどうかを調べると面白いのではと感じました。
それをやる効果として、子ども達には生き方のヒントを身に着けるきっかけにはなると思います。また、自分自身にとっても、これからの時代を生きる大人としての判断基準を明確にすることにもつながります。
ざっくりですが、「偉人分析シート」 を作ってみると面白いかと。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
【偉人の氏名】あなたが伝記を読んだその偉人は・・・
- どんな地図を持っているか(例:数学、統計学、天文学、経済学、法律、帝王学、などの学問や誰から学んだことがその偉人の本質か)
- どんな問題意識を持っていたか(何に違和感を感じたか、発見や発明の元になった視点は何か)
- ルールを新たに決めたか。なぜそのルールを決めたか(これは柔術にルールを与えて柔道にした講道館柔道の生みの親、嘉納治五郎などが書籍内で例として出てくる)
- 仲間を作っていたか(調べることができれば。本書では伊能忠敬の仲間として、師匠の高橋至時がいたことなどが例としてあげられるが、自分で調べるのは少々難しいかも)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
これは大人でも調べるのが難しいかもしれないですが、少しやってみて、子ども達向けにかみ砕いたシートを作りたいと思います。
このシートを考えること自体が面白そう。
試しに、宮本武蔵でやってみました。(手持ちの知識に頼った即席ものなのでご笑覧いただければこれ幸いです)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
【宮本武蔵】・・・
- どんな地図を持っているか: 戦国の世に生まれ、親と戦場で生き抜いたこと(生きるために強くならざるを得なかった環境)
- どんな問題意識を持っていたか: 名をあげるためにはどうすれば良いのか(戦場で戦果をあげて効率的に名を売るためには、という意識)
- ルールを新たに決めたか。なぜそのルールを決めたか: 兵法家の極意として「五輪の書」を著した。戦国時代が終わり、幕府や藩に仕える社会になったルールに合わせたと言える。(ルールを自ら作ったというよりは実績が元で必要とされたという感じか)
- 仲間を作っていたか: 仲間は、わからないですね。。。強いていえば、バガボンドの中では、”おつう”や”沢庵禅師”なんかでしょうが。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ううむ、なんとも難しい。。。
そういえば話はそれますが、宮本武蔵さんといえば、つい最近のバキ道(週刊少年チャンピオン)で、冷凍人間にされてしまいましたね。。。(笑)
そして次に登場するのは、”スクネ”という人物の模様です。
やはり、野見宿禰でしょうか。(同じようなこと考えてる人がいた ⇒ こちら ※ていうかほんまにこの人ずっと書き続けてるよな。。。バキというか板垣先生が好きすぎるんやろう。すごい。)
次はバキで相撲か?さすがに今さらじゃないのか?と思うんだがどうでしょう。
・・・失礼しました。
まとめ
学校で学ぶ意味は何か。未来を創るため。ミライを楽しく生きるため。
そして個人的には大人は、ミライを創るための生き方を子ども達に教えるために学び続けることが大切だと感じました。というお話です。
なかなか難しいかもしれませんが、大人として思考停止して化石にはなりたくないものです。
最後に、答えを書いておきましょう。
法則1 世界を変える旅は「違和感」からはじまる
法則2 冒険には「地図」が必要だ
法則3 一行の「ルール」が世界を変える
法則4 すべての冒険には「影の主役」がいる
法則5 ミライは「逆風」の向こうにある
詳しくは、ぜひ書籍を読んでみて頂ければと思います。
・・・そういえば、歴史を学ぶ意味、という点は別途深掘りしたい気になったので、また別途記事にしますね。
以上。
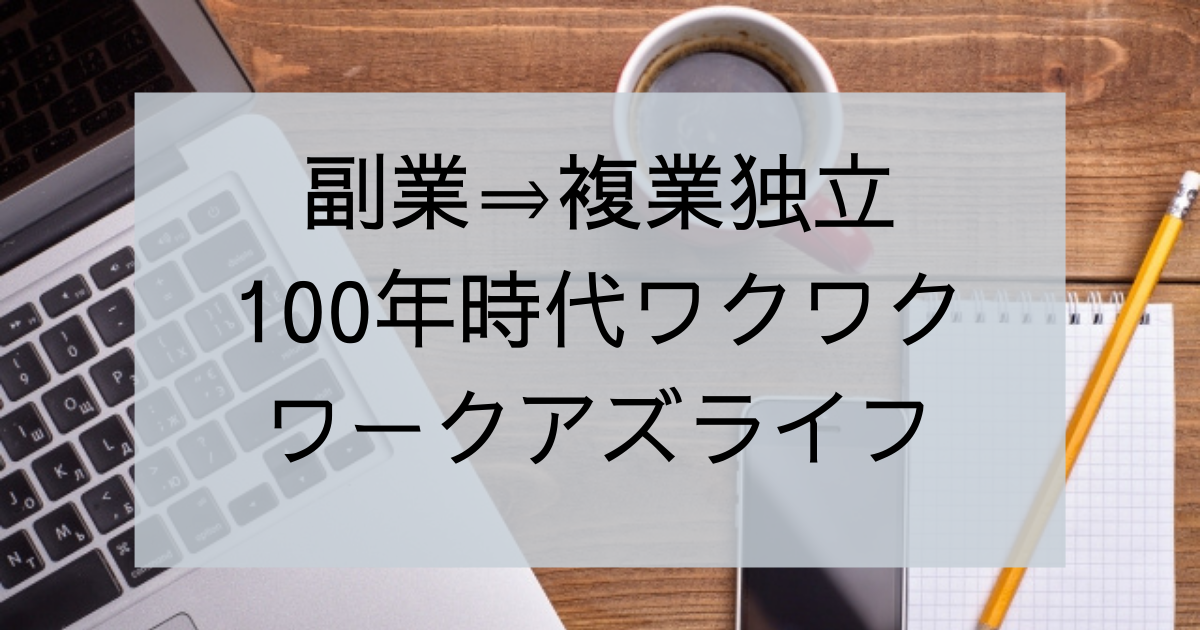

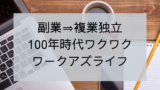
コメント